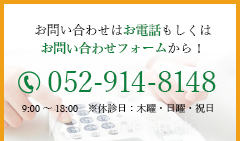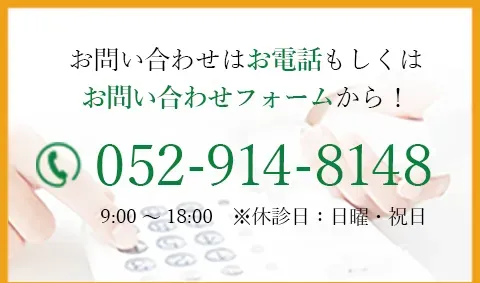入れ歯は保険適用の治療?入れ歯の種類やそれぞれのメリット・デメリット

こんにちは。名古屋市北区大曽根にある医療法人晃生会 光輪歯科です。
失った歯を補う方法の1つに入れ歯があります。入れ歯にはいくつか種類があり、保険適用と自費治療では費用や品質が異なります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の口腔内の状態や予算に合わせて選択する必要があるでしょう。
今回は、入れ歯の種類や費用について詳しく解説します。
入れ歯の種類

入れ歯には、部分的に失った歯を補う部分入れ歯と、上下どちらか、または上下どちらの歯も1本も残っていない場合や、歯の根っこだけが残っている場合に全ての歯を補う総入れ歯の2種類があります。
それぞれに保険適用と自費治療の入れ歯があります。主な入れ歯の種類は、以下の7つです。
・保険適用の入れ歯
・即時義歯(仮義歯)
・ノンクラスプデンチャー
・シリコン義歯
・金属床義歯
・マグネット義歯
・インプラント義歯
それぞれ詳しく解説します。
保険適用の入れ歯
保険適用の部分入れ歯の場合、歯科用レジンと金属のバネ(クラスプ)でできています。人工歯と歯茎の役割をする部分はレジン素材で、金属のバネを残った歯に引っかけて安定させます。そのため、金属が目立つことは避けられません。
総入れ歯の素材は、人工歯と歯茎どちらの部分も歯科用レジンで作られます。人工歯を並べた床(しょう)を、歯茎に吸着させることで入れ歯を安定させます。厚みがあり違和感が大きい、お口に合わないと外れやすい、物を噛み切りにくいなどのデメリットがあります。
即時義歯(仮義歯)
即時義歯(仮義歯)は、抜歯後に使用する入れ歯です。何らかの理由で歯を抜いた後は、歯の根の跡が歯槽骨に残ります。抜歯窩(抜歯後の歯茎・歯槽骨の穴)は徐々に修復されていきますが、骨を覆う粘膜が安定するまでは3〜6か月かかります。
そのため、抜歯直後に型を採取して義歯を作ると、数か月後には歯周組織の形が変化して合わなくなります。
しかし、傷が安定するまで歯を補わずに放置することはできません。特に前歯の場合、抜歯してから入れ歯の作成を始めると、前歯がない状態で何週間も過ごさなければなりません。機能性に問題があるのはもちろん、見た目を気にする患者様が多いでしょう。
即時義歯(仮義歯)を使用すれば、前歯がない状態で過ごすことはなくなります。デメリットとしては、数か月後には合わなくなるため、作り変えが必要なことが挙げられるでしょう。作り替えることを考慮して、保険内で作成するのが一般的です。
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャーは、金属のバネ(クラスプ)を使用しない部分入れ歯です。バネの代わりに歯茎と同じ色の樹脂を使用して安定させます。金属のバネがないため審美性に優れた部分入れ歯です。
シリコン義歯
シリコン義歯は、歯茎に当たる部分を柔らかいシリコン素材で作った入れ歯です。レジン素材打と噛んだときに痛みを感じる方も多いですが、シリコン義歯は歯茎に当たる部分がシリコンで作られているため、しっかり噛んでも痛みが出にくいです。
また、シリコンは歯茎に吸着しやすいため、入れ歯が外れにくいこともメリットです。
金属床義歯
金属床義歯は、床の部分を薄い金属にした入れ歯です。保険の入れ歯は歯科用レジンで作るため、強度を高めるためにある程度厚くする必要があります。この場合、装着時の違和感に悩まされる方が少なくありません。
金属床義歯は保険適用の入れ歯の3分の1程度の薄さで作ることが可能です。金属は強度が高いため、薄く作っても破損する心配がないためです。
床を薄くすれば、違和感を少なくできます。また、金属は熱伝導率が高いので食べ物や飲み物の温度を感じやすいこともメリットでしょう。
マグネット義歯
マグネット義歯は、歯根に磁石(マグネット)を埋め込み、入れ歯側にも磁石を取り付けて入れ歯を固定する仕組みです。磁石の力で固定されるため安定性が高く、外れにくい特徴があります。
ただし、磁石を埋め込む歯根が残っていないと作製できません。ペースメーカーを装着している方も、対象外になることがあります。
インプラント義歯
インプラント義歯は、インプラントと入れ歯を組み合わせる方法です。
上顎または下顎に2本~6本のインプラントを埋め込み、その上にアタッチメントというパーツを取り付けます。インプラントで入れ歯を固定するため、入れ歯の安定性が高く噛みにくい、外れやすいなどの入れ歯の問題を解決できます。
ただし、インプラントは高額な治療であるため、インプラントの本数が多くなると100万円を超える費用がかかる可能性もあります。
入れ歯は保険適用?

入れ歯は保険適用で受けられる治療です。
保険適用の入れ歯では、人工歯と歯茎の役割をする床にプラスチック樹脂の歯科用レジンが使用されます。また、部分入れ歯ではバネ(クラスプ)が金属製です。
保険適用の入れ歯は安価に作製することが可能ですが、金属のクラスプが目立つ、違和感がある、噛みにくいなどのデメリットがあります。
入れ歯を保険で作るときの費用

入れ歯を保険で作る場合の費用は、部分入れ歯か総入れ歯によって異なります。部分入れ歯の場合は、補う歯の本数によっても変動します。
部分入れ歯と総入れ歯を、保険で作る時の費用の目安は以下の通りです。
・部分入れ歯:5,000円~1万5,000円程度
・総入れ歯(片顎):1万円~1万5,000円程度
どちらも3割負担の場合の目安です。
入れ歯を自費診療で作製するときの費用

入れ歯を自費診療で作製するときの費用は、歯科医院によっても違いますが15万円~100万円前後が一般的です。自費診療で作製する入れ歯は、劣化しにくい耐久性に優れた材料を使用するため、違和感が少なく物をしっかりと噛める高品質なものに仕上げられます。
バネが見えない部分入れ歯など、審美性にも優れた入れ歯を作製することも可能でしょう。種類や素材によって大きく費用が変動するので、治療を受ける歯科医院で事前に確認しておきましょう。
保険の入れ歯のメリット・デメリット

保険の入れ歯のメリットは、以下のとおりです。
・費用を抑えられる
・治療期間が短い
・修理や作り直しがしやすい
保険の入れ歯の最大のメリットは、費用を抑えられることです。負担割合によって異なりますが、3割負担の場合5,000円~1万5,000円程度で入れ歯を作製できます。入れ歯を作製する工程も決まっているので、治療期間は1ヶ月〜1ヶ月半ほどです。
保険適用の入れ歯は経年劣化により数年に一度は修理・作り直しが必要です。
続いて、保険の入れ歯のデメリットを確認しましょう。
・経年劣化しやすい
・違和感が大きい
・安定しない
・温度を感じにくい
保険適用の入れ歯は、主に歯科用レジンで作られるため、経年劣化による変色・すり減りを避けられません。プラスチック素材のためにおいも付着しやすいです。
また、歯科用レジンは、強度を確保するために床部分にある程度の厚みを出す必要があるため、入れ歯を装着したときの違和感が大きくなる場合が多いです。床部分が厚いと食べ物や飲み物の温度を感じにくく、入れ歯のフィット感も悪くなるでしょう。
自費の入れ歯のメリット・デメリット

自費の入れ歯のメリットは、以下の通りです。
・保険の入れ歯に比べて寿命が長い
・違和感が少ない
・審美性が高い
自費の入れ歯のメリットは、保険の入れ歯に比べて経年劣化しにくいため寿命が長く、違和感が少ないことです。自費の入れ歯では人工歯にセラミックを使用したり、床の部分を薄い金属で作ったり、使える材料の幅が広がります。
セラミックは強度と審美性に優れた素材であり、長い間きれいな状態を保てます。また、床の部分を薄い金属にすれば、装着時の違和感を抑えながら飲食物の温度を感じやすくできます。
部分入れ歯の場合は、金属のクラスプの素材を変更したり、クラスプがない入れ歯にしたりすることも可能です。
自費の入れ歯のデメリットも確認しましょう。
・費用が高い
・治療期間が保険の入れ歯に比べて長い
自費の入れ歯のデメリットは、費用が高いことです。自費診療の場合は全額患者様の負担になるため、保険診療に比べて費用が大幅に高くなることは避けられません。
また、自費の入れ歯は精密に作られるため、作業工程が多くなります。通院の回数も増えるため、治療期間が保険の入れ歯よりも長くなる場合が多いです。
まとめ

入れ歯は保険適用で受けられる治療です。保険適用であれば、安価に入れ歯を作製することが可能です。
ただし、保険適用の入れ歯では使用できる材料や治療工程に制限があるため、使い心地に満足できない方もいらっしゃいます。そのような場合は、自費診療での入れ歯の作製を検討することも1つの方法です。
入れ歯にも様々な種類があり、それぞれの費用や特徴が異なります。メリット・デメリットを理解したうえで、自分の口腔内の状態や予算に合った入れ歯を選択することが大切です。
入れ歯の治療を検討している方は、一度歯科医院に相談してみましょう。
入れ歯を検討されている方は、名古屋市北区大曽根にある医療法人晃生会 光輪歯科にお気軽にご相談ください。
当院は、歯を治すだけではなく患者さまの悩みを解決する医療を提供できるよう、診療を行っています。虫歯・歯周病治療を始め、ホワイトニングや審美歯科など、さまざまな診療に力を入れております。
名古屋市北区大曽根の光輪歯科はリラックスできる空間作り、患者様への心遣い、最新の設備でニーズに合わせた治療にこだわります。
- お問い合わせはお電話もしくは
お問い合わせフォームから! -
9:00~18:00 ※休診日:日曜・祝日
前の記事 : 妊娠したら歯科検診を受けるべき?時期・受診のメリット・費用・内容を解説
次の記事 : インビザラインとは?メリット・デメリットや費用、期間を徹底解説!
カテゴリー
最新の記事

審美治療
-
セレックシステム
歯の型を採ることなく最短1日でセラミックの白い歯が手に入る最先端のシステムです。

-
ホワイトニング
加齢や遺伝、食生活などによって変色した歯を漂白剤で脱色して白くする方法です。

-
矯正治療
お子さま〜成人まで各年代に合った矯正治療の装置をご用意しております。

メニュー

審美治療
-
セレックシステム
歯の型を採ることなく最短1日でセラミックの白い歯が手に入るシステムです。

-
医療ホワイトニング
加齢や遺伝、食生活などによって変色した歯を漂白剤で脱色して白くする方法です。

-
矯正治療
お子さま~成人まで各年代に合った矯正治療の装置をご用意しております。

-
インプラント
人工の歯根を植え顎骨と固定して、それを土台に人工の歯を装着する方法です。

メニュー
治療について
- » 治療の流れ
- » 虫歯治療
- » 歯周病治療
- » 入れ歯治療
- » 口腔外科治療
- » 小児歯科
- » レーザー
- » ブルーラジカル治療
- » 医療ホワイトニング
- » 予防歯科
- » 矯正治療
- » 審美歯科
- » インプラント
- » セレックシステム
- » 口腔機能低下症
(食べにくい・飲み込みにくい) - » 口腔機能低下症の検査
- » 特殊外来(ドライマウス・口臭)
- » スポーツ歯科
- » 訪問歯科診療
- » 妊産婦健診
- » よくある質問
- » 症例集
- » 医療費控除について